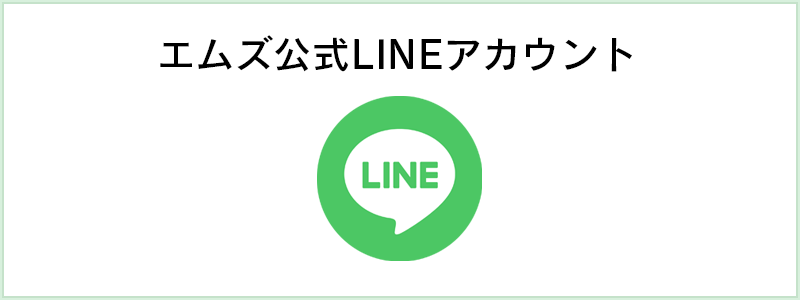| ペルル岸里 |
【2023年7月施工】
・クロス張替・リペア工事
・畳表替・襖、障子張替
・カーペット張替
・ハウスクリーニング他

| ルネ・コンフォートアベニュー |
【2023年5月末施工】
・キッチン新調・洗面台新調
・風呂新調・トイレ新調
・クロス張替
・ハウスクリーニング他

| メロディーハイム住道ガーディア |
【2023年4月末施工】
・クロス張替・CF張替
・リペア工事・畳表替
・襖、障子張替
・ハウスクリーニング他
エムズはお客様とのコミュニケーションを第一に考え、大切な家づくりを、一歩一歩着実に進めます。
建築の流れ
▼STEP 1
ご相談
お客さまのご要望やご家族構成、ご予算などを充分にお伺いして、ご提案の準備に入ります。
▼STEP 2
土地調査
敷地の形状や現況、周辺環境、法的規制などを徹底調査。プランづくりに反映します。
▼STEP 3
地盤調査
地盤が建物の重量に耐えうる強さ(地耐力)を持っているか、スウェーデン・サウンディング方式(SS式)にて調査し、そのデータを元に適切な基礎の設計を行います。
▼STEP 4
建物のご提案
お客様のご希望、ライフスタイルに合わせて、都市型・和モダン・輸入住宅風などご希望の間取りや設備外観をイメージできるよう、具体的にわかりやすくご提案します。
▼STEP 5
建築請負契約
本設計、見積書等、ご契約内容にご了解をいただけましたら、建築請負契約を締結していただきます。
▼STEP 6
詳細打ち合わせ
内部仕様・外部仕様の設定、設備・機器の配置など、設計内容の詳細を決定・ご確認いただきます。その後、建築確認申請の手続きをいたします。
▼STEP 7
着工
お客さまと当社の積算・設計・工事・コーディネーター・営業の各担当者とで、工事内容、工事期間などの最終確認を行い、建物の位置を決める地縄張りにお立ち会いいただいたうえ、建築に着手します。
▼STEP 8
上棟
構造躯体が組み上がり、屋根板が張られると、工事は仕上げの段階に。電気配線などの設備工事や内装・外装などの工事が始まります。
▼STEP 9
完成・ご入居
内装・外装・設備の工事を終えると、ご新居の完成です。各工程での審査に加え、お客さまの立ち会いによる厳正な竣工検査を行います。お建物引渡書や保証書などの証書類と鍵をお渡しして、いよいよご新居での暮らしのスタートです。
▼STEP 10
アフターサービス
永く安心していただけるよう、屋根、外壁、構造躯体の10年保証システムを実施。さらに、定期巡回サービスやアンケートによるアフターメンテナンスサービスも行っています。
建築Q&A
-
注文住宅と規格型の住宅の違いは?
-
規格型の住宅とは、住宅メーカーなどが手がける大量生産の住宅です。同じような外見の住宅をよく見かけることがありますが、それらは建てる人の希望を全て取り入れた家とは言えません。逆に、注文住宅は一からプランニングしていくもので、工務店や注文住宅業者が手がけるものです。建てる人の希望やこだわりを実現し、自分だけの住まいを手に入れることができます。
-
注文住宅はどれくらい思い通りの家がつくれるの?
-
注文住宅は規格型住宅などと比較し制約が少ないので、デザイン、間取りなど自由に選ぶことができます。また、収納のプランや介護向けのプランなど、細かい点も決めることができます。
-
狭い土地だけど対応してもらえるの?
-
狭小敷地や変形敷地に、自由設計の利点を活かし快適な住宅を建てることができることこそ、注文住宅の特長です。「大きな窓」、「吹き抜け」、「中庭」など採光と通風を確保し、開放感と快適性を高める方法があります。
-
注文住宅って高い?
-
注文住宅は予算に応じて、きめ細かい提案ができます。使用する建材やプランの細かいところまで自由に選択することができますので、費用をかけたいところ、コストダウンをしたいところを分けて考えることが可能です。
-
自由設計の注文住宅なら制約はないの?
-
基本的には制約はありませんが、建築基準法など法で定められた基準がクリアされていなければなりません。また、昨年建築基準法が改正され、「どのような建材を使うか」「設備に何を使うか」といった細かい仕様の規制がなくなり、一定の基準を満たせば以前よりも自由な家づくりが実現可能となりました。
-
将来、増改築をする場合のことも考えたいのですが…
-
構造にもよりますが注文住宅は増改築が自由にしやすい、という優れた点があります。規格型住宅では構造上変更できない部分が多く、自由な増改築ができない場合が多くあります。
-
建築中の建物のチェックはどのようにされているの?
-
第三者機関を使い、検査や保証を行っております。またそれだけではなく、社内での独自のチェック体制も整えております。完成後お引き渡しの際は、検査報告署・保証書をお渡ししております。
-
プラニングは無料なの?
-
建築のご相談から、調査、プランニング、概算見積まで、費用は一切いただきません。まずは疑問点やご希望などからご相談ください。
-
地盤調査の費用はどれくらいかかるの?
-
以前は小川や水田のあった場所など、軟弱地盤が考えられる場合は地盤調査を行います。軟弱地盤であった場合は、相応の地盤改良工事が必要となります。木造やプレハブなど一般の建物の地盤調査の場合、1宅地あたり3箇所程行い、1件あたり6万円ほどになります。調査結果には基礎計画や地盤補強対策等の診断が盛り込まれます。地盤改良工事は、一般におおよそ100~150万円程度必要と思われます。
-
耐震と免震の違いは?
-
耐震は、建物全体の強度を高めた工法で、地震など強い揺れによる建物の倒壊を防ごうとするものです。一方免震とは、建物の足元を地面から切り離し、その間に特殊な免震装置を組み込むことによって地震の激しい揺れを受け流す構造のことをいいます。これまでは主にビルなどに用いられていた技術ですが、最近では住宅にも用いられるようになってきました。
-
SE構法にはどんな保証制度があるの?
-
SE構法は、第三者機関による保証制度があり、SE構法住宅性能保証制度本部が建物保証をします。品質基準に基づき、不具合(瑕疵)があるかどうか、基礎配筋検査、構造体検査、防水検査の3回にわたり行われます。この検査を実施した物件を「SE構法の住宅」として認定し、「SE構法の住宅」住宅性能保障規定に基づく保証書が発行され、建物引き渡し後10年間を目処として、建物瑕疵の保証をします。万一建物に不具合(瑕疵)が起こった場合には、NCN(SE構法住宅性能保障制度本部)がその保証費用のうち一定金額を保証します。
-
SE構法と在来の工法はどう違うの?
-
在来工法に比べSE構法は、大空間・大開口が実現でき、耐震性にも優れています。また、SE構法の住宅は、木造の構造計算を行いますので、柱梁部材、接合金物の強度の判定や、建物の剛性バランス評価といった安全性能を評価します。さらに、SE構法住宅だけが入れる重量木骨プレミアムパートナーによる保険があります。
-
次世代省エネ基準とは何ですか?
-
国土交通省の外郭団体、(財)建築環境・省エネルギー機構によって認定される評定で、高断熱・高気密・計画換気の確かな施工により住宅性能の向上を目指す、高性能住宅施工基準です。建築主の判断基準による性能規定、もしくは、設計・施工の指針による仕様規定により、次世代省エネ基準を満たす住まいを建てることができます。平成11年には改正により、断熱・気密化が進展しました。断熱・気密性が低い住宅では、暖冷房の使用が基本となっている昨今ではエネルギー効率が極端に悪いと言えるためです。
-
内断熱と外断熱はどんな違いがあるの?
-
内断熱(充填断熱工法)は柱の間にグラスウールなどの断熱材を入れる方法のことをいい、外断熱(外張り断熱工法)は、柱の外に断熱材を張り巡らす方法のことをいいます。日本ではこれまで内断熱が一般的でしたが外側の通気層の幅が狭い内断熱工法では、壁の内部で発生する内部結露が起きる可能性が高くなります。外断熱工法では、構造躯体の屋外側に断熱材を施工し通気層を20mm確保することで、内部結露を防ぎ、構造躯体を守ることができます。
-
住宅金融公庫などの融資手続きはどのようにしたら良いの?
-
お客様によって色々なケースがございますが、安心して返済できるローン計画から住宅金融公庫融資の申請、金融機関のご紹介まで、きめ細かく対応いたします。
リフォームの流れ
▼STEP 1
事前準備
現状の問題点を確認し、お客様のご要望をお伺いします。工事内容によって必要な施工担当とともに、ご自宅の調査(下見)を行います。お打合わせと下見の結果を元に、一度お見積を作成し、大よその予算をご確認いただきます
お問い合わせ→初回打ち合わせ→現場下見→ご提案プラン・見積もりのご提示
▼STEP 2
内容検討・ご契約
施工業者を決定します。契約書の内容を確認します。契約約款・保証期間・見積書・施工図面・支払条件などを再度ご確認下さい。契約時のトラブルを防止する目的で、なるべく議事録を作りましょう。一般的に施工会社には、打合わせ記録がありますので、施工会社が作成した記録を確認する方法でもよいでしょう。着工に向けて、マンションの場合は、管理組合への申請、また近隣挨拶を行います。また、着工前に再度確認の打ち合わせを行い、工事内容に間違いがないか確認します。追加や変更がある場合は、着工前までに金額や項目を確認しておきます。
最終見積もりのご提示→ご契約→契約金のお支払い→着工前打ち合わせ
▼STEP 3
施工着手
現状の問題点を確認し、お客様のご要望をお伺いします。工事内容によって必要な施工担当とともに、ご自宅の調査(下見)を行います。お打合わせと下見の結果を元に、一度お見積を作成し、大よその予算をご確認いただきます。
近隣の方へのご挨拶→着工→完成→お引渡・お支払い
リフォームQ&A
-
リフォームはどんなことができるのですか?
-
設備機器の交換や壁紙の貼り替え等小規模なリフォームから、キッチン・お風呂場など部位別に行うリフォーム、外壁塗装、耐震補強、間取り変更など空間をつくり変える大掛かりなリフォームまで、さまざまな内容があります。 マンションの場合は、共用部分・専有部分が明確に決まっておりますので、共用部分に対するリフォームは出来ません。ご注意下さい。
-
中古物件の購入を検討している段階から相談できますか?
-
もちろんご相談していただけます。希望するリフォームが出来るかどうか、構造や規約などのチェックが必要ですので、検討段階からのご相談をおすすめします。
-
図面は必要ですか?
-
ご準備いただくと、打合わせがスムーズになりますが、無くても室内を調査する際に確認できます。特に構造を変更するリフォーム(壁を取る等)の際はなるべくご用意下さい。
-
契約書・見積書はどこを確認すればいいでしょうか?
-
前提としては、まず、打合わせした内容が全て入っているかをご確認下さい。 加えて、見積もりの諸条件も問題になりますので、ご注意下さい。(例えば、駐車場のスペースを空けておくとか等) 「工事請負契約書」「請負約款」「図面・仕様」の確認と 疑問点については些細なことでも、契約前にクリアーにしておきましょう。
-
できあがりのイメージはどういう方法で確認できるのでしょうか?
-
設備機器はメーカーのショールームを利用して確認する事ができます。間取り変更等の場合は、CADを利用したCG等でイメージを確認していただきます。また弊社が実際に建築しました物件を見てイメージして頂くことも可能です。
-
リフォームローンを検討していますが、紹介してくれますか?
-
銀行でリフォームローンの商品が用意されております。お気軽にご相談ください。
-
マンションはどこまでリフォームできますか?
-
共用部分以外は基本的に可能です。マンションの規約によっても細かく決まりがありますので、詳細を規約で確認する必要があります。 構造躯体やサッシ、玄関ドア、バルコニーは共用部分ですので、変更する事は出来ません。
-
建て替えかリフォームか悩んでいます・・・
-
それぞれに、メリット・デメリットがあります。建替えの場合は、確実に仮住まいが4~5ヶ月必要になりますが、リフォームの場合住まいながらの工事も可能です。但し、現在のお住まいにもよりますが、旧耐震基準で建築されている場合、リフォームをする際、同時に耐震改修もする必要(おすすめ)があります。コストを含め、平行して検討される事をおすすめいたします。
-
バリアフリーを検討しています、費用はどの位かかりますか?
-
バリアフリーでも手摺を1ヶ所取付だけであれば数万円~も可能ですが、段差をなくす、開き扉を引き戸にするなどの工事の場合はコストは変わってきます。詳しくはお問合せ下さい。
-
リフォームにも減税の制度があると聞いたのですが‥
-
平成21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。 「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」 一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。


-200x200.jpg)





-3-200x200.jpg)